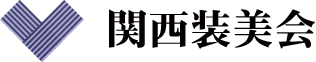理 念

「着物が織りなす美を極める」
着物は、長い歴史の中で受け継がれ、
日本の四季と深く関わる独特の形と装飾で表わされた
世界に誇れる衣服です。
世代を超えて、多くの方々に「着物」の素晴らしさを
知っていただき、
そして、「着物の装い」を際立たせるよう、
着付けの技術を習得し、
向上を図ることを目的として設立いたしました。
関連教室
アカデミー着付け教室(和歌山県-御坊市)
かんな着付け教室(大阪府-箕面市)
ひまり庵着付け教室(大阪市-淀川区)

資格取得
着物の自装ができることができ、尚且つ、着付け講師としての資格を受けたい方は、講師資格認定を受験することが可能。
(実技試験筆記試験)
合格された方には、免状及び看板の授与。
※講師資格取得者-のべ100名

講習会の実施
2年に一度程度、講師の方々にお集まり
いただき、振袖などの着付けを練習し、スキルアップに繋がる講習会を開催しています。

~着物のこと~
着物は、二千年の歴史があり、着物ならではの「色合い」、「文様」や「柄」など、その美しさには、心を奪われます。また、着物は、身に付けることにより、立ち居振る舞いに影響し、人を優雅な気持ちにさせることも魅力の一つです。着物を通して、四季折々の情感を感じるところも醍醐味といえるでしょう。
◆着物の歴史について
着物は、日本の歴史とともに、形や役割を変えながら発展しました。各時代により、着物の特徴や流行は異なりますが、常に、日本の文化を代表する衣裳として、人々に親しまれています。
「奈良時代(710〜794年)」
中国・唐の影響を受けた「裳(も)」や「袍(ほう)」などの装束が用いられ、公家や貴族階級を中心に、男女ともに重ね着のスタイルが発展。
「平安時代(794〜1185年)」
貴族女性は「十二単(じゅうにひとえ)」を着用。色の重ね方(襲の色目)に美意識が宿る。男性は「直衣(のうし)」や「狩衣(かりぎぬ)」などを着用。
「鎌倉・室町時代(1185〜1573年)」
武士階級の台頭により、実用性が重視される。簡素で動きやすい装いが増加。室町後期には小袖(こそで)が一般化し、現代の着物の原型となる。
「安土桃山時代(1573〜1603年)」
豪華な織物技術が発展。武将や富裕層が贅沢な小袖を着用し、金箔や刺繍が施された絢爛な装いが流行。
「江戸時代(1603〜1868年)」
庶民にも小袖が広まり、「着物」という呼称が一般化。町人文化が栄え、染色・紋様が発達。武士・町人・農民それぞれに適した着物スタイルが確立。
「明治時代(1868〜1912年)」
西洋化政策により、洋装が推奨される。一方で和装も公私で使用され続け、和洋折衷スタイルも登場。男性の袴姿が制服化される場面もある。
「大正・昭和時代(1912〜1989年)」
女性の洋装化が進行。戦後は普段着としての着物が急減し、礼装・行事用として位置づけられるようになる。高度経済成長期には高級品としての着物文化が復興する。
「現在」
日常着としての着物は減少したが、成人式、結婚式、卒業式などの式典や観光地での体験着物として需要が継続。近年はモダンなアレンジとしても再注目されている。
◆季節と着分けについて
着物の世界では、季節に合わせて、身に付けるものが変わる「衣替え」の決まり事があります。
袷の季節:一般的に10月から5月末まで着用。
表地に裏生地を合わせた仕立て方で、裾の部分には、「八掛」と呼ばれる生地で仕立てられています。結婚式や式典など、冷暖房が完備されていることから、夏場でも、留袖などは、 袷の着物を着用する場合もあります。
着物:「綸子」・「縮緬・」「紬」・「御召」・「ウール」・「木綿」など
帯:「唐織」・「錦織」・「綴れ織」・「塩瀬」・「紬」・「綸子」・「博多織」・「木綿」
半衿:「縮緬」・「塩瀬」など
単衣の季節:一般的に6月と9月の2カ月間 着用。
裏地を付けずに仕立てる方法で、6月に着用する単衣の着物は、涼やかな模様や色目を選び、夏帯とともに、夏仕様の小物を用います。また、9月に着用する単衣の着物は、秋を意識した模様や色目を選びます。
着物:「絽紬」・「絽縮緬」・「夏結城」・「夏大島」・「木綿」・「紗袷」など
帯:「紗袋」・「絽綴」・「紗献上」・「絽」・「麻袋」・「絽紬」・「半幅帯」など
半衿:「絽縮緬」・「楊柳」など
薄物の季節:一般的に7月と8月の2カ月間 着用。
単衣同様、裏地を付けずに仕立てる方法で、絽や紗と呼ばれる透ける生地を用います。
帯・長じゅばん・小物なども夏素材のもので合わせます。近年は、温暖化の影響により、
気温に合わせて、必ずしも、7月と8月とは限らない。
着物:「紗」・「絽」・「麻」・「絹紅梅」・「浴衣」など
帯:「紗」・「絽」・「麻」・「羅」・「絽綴」・「紗献上」・「半幅帯」など
半衿:「絽」・「紗」・「麻」
◆季節の模様・モチーフについて
四季がある日本では、「春」・「夏」・「秋」・「冬」に応じて、柄選びをすると、季節感が楽しめます。年中行事に合わせた柄選び、また、季節の先取り(半月くらい)すると、粋な印象が演出できます。
季節の柄 例
| 月 | 柄 |
| 1月 | 宝船・羽子板・鶴・亀・凧・松竹梅・千両・鈴-など |
| 2月 | 梅・椿・猫柳・ふきのとう・鴬-など |
| 3月 | 桜・ひな祭り・貝合わせ・土筆・雲雀・菜の花-など |
| 4月 | 牡丹・木蓮・辛夷・朧月・蝶-など |
| 5月 | つつじ・鯉のぼり・鎧・菖蒲・あやめ・牡丹-など |
| 6月 | 藤・紫陽花・葵・びわ・蛙-など |
| 7月 | 天の川・風鈴・団扇・朝顔・金魚 など |
| 8月 | 撫子・ひぐらし・灯籠・花火・桔梗 など |
| 9月 | 菊・薄・りんどう・萩・蜻蛉 など |
| 10月 | 秋草・紅葉・栗・柿・稲穂 など |
| 11月 | 柊・銀杏・落ち葉・松ぼっくり など |
| 12月 | 雪輪・寒椿・雪うさぎ・水仙 など |
◆帯揚げ・帯締めについて
「帯揚げ」と「帯締め」は、帯結びを美しく保ち、着物姿を華やかに演出するための重要なアイテムです。「帯揚げ」は、本来、「帯枕を隠すための布」で、機能重視の脇役でしたが、江戸時代の後期以降、おしゃれな色柄が登場し、装飾品としての役割が強まりました。着物のシーンや好みに合わせて使い分けることで、より一層着物姿を楽しめます。
※帯揚げと帯締めの色を「対比させる」と引き締まる同系色でまとめるのも上品ですが、あえて反対色を使うと、メリハリが出ます。
※季節ごとに「色だけでなく素材」も変える
「帯揚げ」は、夏には絽や紗などの透け感のある素材、冬は縮緬素材などで暖かみを演出します。「帯締め」は、季節に関係なく通年使えるものとされていますが、夏場は、レース組みなどの帯締めが涼しさを演出できます。